 |
The�@Beatles�@Tribute�@Band�@SOMETIME�@Official�@Site |
 |
The�@Beatles�@Tribute�@Band�@SOMETIME�@Official�@Site |
|
| �u�d���l ���B�b�N�v | ||||
|---|---|---|---|---|
�@�U�O�N��Ɋ��� �����p���̒j���f���I�A�s�[�^�[���S�[�h���̃f�r���[�E�V���O���u���Ȃ����E�v�iA World Without Love�j���|�[���E�}�b�J�[�g�j�[�ɂ����̂ł��邱�Ƃ͂悭�m���Ă���B �����p���̒j���f���I�A�s�[�^�[���S�[�h���̃f�r���[�E�V���O���u���Ȃ����E�v�iA World Without Love�j���|�[���E�}�b�J�[�g�j�[�ɂ����̂ł��邱�Ƃ͂悭�m���Ă���B�@�����A�|�[���̓s�[�^�[�̖��ŏ��D�̃W�F�[���E�A�b�V���[�ƕt�������Ă���A�W�F�[���̎��Ƃɋ��������قǂ̒��ł������B���̊W�Ńs�[�^�[�����Ȃ��˗�����A�|�[���������̂����̐��N�O�ɏ����Ă������̋Ȃ��B �@�P�X�U�S�N�Q���Ƀ����[�X���ꂽ�u���Ȃ����E�v�́A���N�S���ɑS�p�V���O���`���[�g�Ńr�[�g���Y�́u�L�����g�E�o�C�E�~�[�E�����v���R���Ƃ��Q�T�A���łP�ʂ��l���B����ɁA�A�����J�̃r���{�[�h�E�g�b�v�P�O�O�ł��P�ʂ��l����������𐬂��������B �@�|�[���ɂ�邫�ꂢ�ȃ����f�B�E���C���ƋC�̗������t�b�N�A�s�[�^�[�E�A�b�V���[�ƃS�[�h���E�E�H�[���[�̗J�����܂R�[���X�E�n�[���j�[���u�₩�ŐS�n�悢�B https://www.youtube.com/embed/eDHPAenvTQI �@�����āA���̋Ȃ��������ĂĂ���̂��A�G���N�g���b�N�P�Q���M�^�[�ɂ��I�u���K�[�g�ƃ\�����B �@�f�C�u�E�N���[�N�E�t�@�C�u�́u�r�R�[�Y�v���v�킹��I���K�����������t�ł�Ԃ�D���Ēቹ���ƊJ������▭�ɐD����������b�N���A�d���ȃx�[�X�̃��Y���Ƒ��܂��āA�ėp�ȃo���[�h�ɂȂ肪���ȋȂɖ������ƃ_�C�i�~�Y����^���Ă���B �@���̃M�^�[�͂��������N���e���Ă���̂��A�����ƋC�ɂȂ��Ă������A�G����C���^�[�l�b�g�Œ��ׂĂ��^���̏ڍׂ͂킩��Ȃ������B�������A�p���̃Z�b�V�����E�M�^���X�g�̑������r�b�O�E�W���E�T���o����X�^�W�I�E�~���[�W�V��������̃W�~�[�E�y�C�W���L���N�X��[���A�g���E�W���[���Y�A�y�g���E�N���[�N�Ƃ����������̃r�b�O�l�[���̐������̋ȂɎQ�����Ă��邱�Ƃ͎��m�̎����ł��邵�A���̋Ȃɂ��Ă������ẴZ�b�V�����E�M�^���X�g���Q�����Ă���ł��낤���Ƃ͗e�Ղɑz�����ł����B �@�ǂ����Ă��m�肽���ĉp��Ńl�b�g���������Ƃ���AVic Flick�i���B�b�N�E�t���b�N�j�Ƃ������O�ɍs�����������B �@�C�M���X�̃Z�b�V�����E�M�^���X�g�ŁA�g���E�W���[���Y�A�N���t�E���`���[�h�A�|�[���E�}�b�J�[�g�j�[�A�_�X�e�B�E�X�v�����O�t�B�[���h�A�G���Q���x���g�E�t���p�[�f�B���N�A�o�[�g�E�o�J���b�N�A�i���V�[�E�V�i�g���A�G���b�N�E�N���v�g���A�W�~�[�E�y�C�W�ȂǁA�Q���������R�[�f�B���O�͖����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B �@�����āA�����Ƃ����B�b�N�E�t���b�N�̖���L���ɂ����̂��u�O�O�V�W�F�[���Y�E�{���h�̃e�[�}�v���B https://www.youtube.com/embed/ye8KvYKn9-0 �@�O�O�V�V���[�Y��w�^�钆�̃J�E�{�[�C�x�w�~�̃��C�I���x�Ȃǐ������̉f�批�y�Œm����C�M���X�̍�ȉƃW�����E�o���[������y�c�W�����E�o���[�E�Z�����̃M�^���X�g�ł��郔�B�b�N�E�t���b�N�́A�܂��A�W���[�W�E�}�[�e�B�����E�I�[�P�X�g���̃����o�[�Ƃ��āA�r�[�g���Y�̑�P��f��w�A�E�n�[�h�E�f�C�Y�E�i�C�g�x�Ń����S���X�����܂悤�V�[���̃o�b�N�ɗ����u�����S�̃e�[�}�vThis Boy�ł����D�Y���M�^�[��e���Ă���B https://www.youtube.com/embed/GIvEc4yhdpM �@�u���Ȃ����E�v�̃��R�[�f�B���O�ɂ��ă��B�b�N�́u���H�b�N�X�̂P�Q���M�^�[�����߂Ďg�������A���낵�������������ėǂ��T�E���h�ł͂Ȃ������B�ł��A�ŏI�I�ɂ��܂������āA���R�[�f�B���O�ɐV�����T�E���h�ƃL�����N�^�[����������B�i�����j�s�[�^�[���S�[�h���̓v���t�F�b�V���i���łƂĂ��ǂ��d���������B�v�ƌ���Ă���B �@���ǂ��T�E���h��Njy����̂ɗ]�O���Ȃ����B�b�N�́A�C�M���X���̃t�@�Y�E�{�b�N�X�u�g�[���E�x���_�[�v�̊J���ɂ�����Ă���B�Q�O�P�R�N�A�M�^���X�g�A��ȉƁA�w���҂Ƃ��Ă̒��N�̊������]������A�A�����J�� National Guitar Museum ���琶�U���J�܂������Ă���B �@�������P���̃V���O���Ղł����Ă��A�Ȃ̐��藧����Q���~���[�W�V������H���Ă����Ύv���������Ȃ������ɋ����A�m��Ȃ����E�ւ̓����ɗ����Ƃ�����B��������R�[�h�N�W�̖����݂ł���B
|
||||
| ���O�̗R�� | ||||
�@�u�r�[�g���Y�v�Ƃ������O���A�o�f�B�E�z���[�̃o���h�A�u�N���P�b�c�v�Ɉ���ł���ꂽ�A�Ƃ����b�̓t�@���̊Ԃ� �͂悭�m���Ă���B �͂悭�m���Ă���B�@�l�����̂̓W�����ƃX�`���A�[�g�E�T�g�N���t�B �@�G�����B�X�A�`���b�N�E�x���[�A���g���E���`���[�h�A�t�@�b�c�E�h�~�m�A�J�[���E�p�[�L���X�Ƃ������X�^�[�����ƕ���ŁA�ނ炪��D���������̂��o�f�B�E�z���[�ł���B �@�P�X�R�U�N�A�����J�A�e�L�T�X�B���܂�̃o�f�B�E�z���[�́A�P�X�T�U�N�Ƀf�b�J�E���R�[�h����f�r���[�B �@�P�X�T�V�N�T���Ƀ����[�X�����hThat�fll Be The Day�h���S�āE�S�p�P�ʂ��L�^���A���̌���A�hWords of Love�h�@�hPeggy Sue�h�@�hNot Fade Away�h�Ȃǂ������[�X�B �@�P�X�T�W�N�ɂ́w�G�h�E�T���o���E�V���[�x�ɂ��o������ȂǁA��҂ɐ��Ȑl�C�������A�P�X�T�X�N�Q���Q���A�c�A�[���A�ړ��̂��߂̔�s�@���ė����Q�Q�̎Ⴓ�ŋA��ʐl�ƂȂ����B �@���悵�Ă�����l�̃��b�N�E�X�^�[�A���b�`�[�E���@�����X�i�u���E�o���o�v�̃q�b�g�Œm����j�ƃr�b�O�E�{�b�p�[�����S�����B �@���̓��́u���b�N���E���[���̎����v�ƌĂ�A�P�X�V�Q�N�ɑ�q�b�g�����h���E�}�N���[���́u�A�����J���E�p�C�v�ł����̂��Ƃ��̂��Ă���B �@���b�N���E���[���Ƃ����ǂ��A�܂��r�b�O�o���h�E�X�^�C�����嗬�����������A�M�^�[�A�x�[�X�A�h���������������ʼn��t���Ȃ���̂��o�f�B�̃X�^�C���͐V�N�ŁA�����̃o���h���e�������B �@�������A�W�������|�[�����W���[�W����O�ł͂Ȃ������B �@�N�I���[���������߂Đ��������R�[�h�́hThat�fll Be The Day�h���������A�W���[�W�����[�h�E�{�[�J�����Ƃ�hCrying Waiting Hoping�h �͉��ςݎ���̏d�v�ȃ��p�[�g���[�������B �@�w�r�[�g���Y�E�t�H�[�E�Z�[���x�ł́hWords of Love�h���J���@�[���Ă���B �@�W�����ƃ|�[����������������I���W�i���Ȃ�����Ă����̂��A�v���̍�ȉƂ��Ȃ����A�̎肪�̂��Ƃ������Ƒ̐���������O����������ɁA�����ō�Ȃ��ĉ̂��Ƃ����o�f�B�̃X�^�C�����v�V�I�ŁA���̂��Ƃɂ����������������炾�����B �@�܂��A�����̃C�M���X�ł̓A�����J���̃M�^�[�̓���͓���A�������������������߁A�o�f�B���e���X�g���g�L���X�^�[�̓M�^���X�g�̓���̓I�������B �@�W���[�W�͎��ƒ��m�[�g�ɃX�g���g�L���X�^�[�̊G���菑���Ă����Ƃ����B �@�i���ۂɃW���[�W����ɓ����̂͂����ƌ�A�P�X�U�T�N�ɃW�����ƈꏏ�ɔ������\�j�b�N�u���[�̃X�g���g���ŏ��ł���B�j �@���x�̋ߎ��������W�������A�l�O�Ń��K�l�������邱�Ƃ��}��Ȃ��Ȃ����̂��A���Ԃ����K�l���g���[�h�}�[�N�ł������o�f�B�̉e�����ƌ����Ă���B �@�o���h�A�ȍ��A�t�@�b�V�����ȂǁA������ʂŃo�f�B�̉e���͑傫���������A�����ЂƂA�W����������Ă����̂��A�o���h���������B �@�o�f�B��������u�N���P�b�c�v�ɂ́A�R�I���M�ƃX�|�[�c�̃N���P�b�g�̓�̈Ӗ������邱�ƂɋC�Â����W�����́A�����̃o���h�ɂ������悤�Ȗ��O���ق����Ǝv�����B �@��l�ł��ꂱ��l�����������A�X�`�����v�������̂��J�u�g���V�B�@ �@�Ԃ���hbeetles�h�ł͂Ȃ��hbeatles�h�ɂ���A�r�[�g���y���z�N������B �@�r�[�g���Y�Ƃ������O�����Ƃ��A���̃����o�[�͂�����ƕς��Ǝv�������������A�W�����͓��ӂ��Ɍ������B �u�_�u���~�[�j���O�ɂȂ��Ă��邩��ō������B�N���P�b�c�݂����ɂˁB�v �@�������A���̘b�ɂ̓I�`������B �@�|�[���ɂ��A��ɃN���P�b�c�̃����o�[�Ɖ�@�����A�o���h���̘b�ɂȂ����B �@�u�r�[�g���Y�Ƃ������O�͂��Ȃ�������q���g����ł���B�v �@�Ƃ��낪�A�A�����J�l�̔ނ�͒N�ЂƂ�N���P�b�g�Ƃ������Z��m��Ȃ������̂��B
|
||||
| �}���g���@�[�j�͂��߂� | ||||
�@�|�[���E�}�b�J�[�g�j�[���t�B���E�X�y�N�^�[�E�v���f���[�X�ɂ��A���o���w���b�g�E�C�b�g�E�r�[�x�������Ă����̂͗L���Șb���B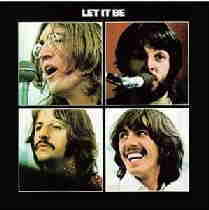 �@���_�ɖ߂�A�I�[���@�[�_�r���O�Ȃ��ŁA���������̂���̂܂܂̉��t�����^����Ƃ����̂����������̃R���Z�v�g�ł������̂ɂ�������炸�A�u�E�H�[���E�I�u�E�T�E���h�i���̕ǁj�v�̋������s�����̂́A�G�R�[��G�t�F�N�g�̑��p�A�I�[�P�X�g���⍇���̃I�[���@�[�_�u�A�M�^�[�\���̍����ւ��A�Ƃ������S�������̂��Ƃ��������炾�B �@���ł��A�|�[���������Ƃ��C�ɂ���Ȃ������̂��u�U�E�����O�E�A���h�E���C���f�B���O�E���[�h�v�̃A�����W�������B �@�|�[���ɂ́A�Y��ȃ����f�B���������o���[�h���������Ƃ��Ă��u���������̓��b�J�[���v�Ƃ������������������A���t�ƂƂ��Ẵr�[�g���Y�̋Z�ʂƃZ���X�ɂ͐�̎��M�������Ă����B �@���ʂȑ�������ؔr�������V���v���ȉ��t�ł������̋Ȃ̎����������������ƍl���Ă����̂ɁA����ɑ�ȃI�[�P�X�g���⏗���R�[���X���������Ă͂��܂�Ȃ��B ����ł͌��_��A�i�f�����a�������j�ǂ��납�A�x�^�ȃC�[�W�[���X�j���O���y�ł͂Ȃ����B �@�r�[�g���Y�i���m�����}�b�J�[�g�j�[�j�̍�ȉƂƂ��Ă̕]������߁A�����Ƃ������̃J���@�[�̂́u�C�G�X�^�f�C�v�����A���̋Ȃ̐���ے��ł���㒅�������B �@�|�[�������̒��ō�Ȃ����Ƃ������ƂŒm����u�C�G�X�^�f�C�v���ŏ��ɒ������Ƃ��A�v���f���[�T�[�̃W���[�W�E�}�[�e�B���́u���̋Ȃɂ̓w���B�[�ȃh�������M�^�[���v��Ȃ��B�X�g�����O�X�͂ǂ����낤�B�v�ƒ�Ă����B �@���̂Ƃ��A�u�X�g�����O�X�v�ƕ����ĊÂ����邢���[�h���y��A�z�����|�[���͑����Ɍ������B �@�u�}���g���@�[�j�Ȃǂ��߂B�v �@�ŏI�I�ɁA�V���v���Ȍ��y�l�d�t���������邱�ƂɂȂ�A����ɂ̓|�[�����[�������B�i���B�u���[�g�͈������ȂƂ����̂��|�[���̒����������j �|�[���ȊO�̃����o�[���Q�����Ă��Ȃ��u�C�G�X�^�f�C�v�������[�X����ɂ������Ă̓\�����`�łƂ����������������������A�}�l�[�W���[�̃u���C�A���E�G�v�X�^�C���́u����̓r�[�g���Y�̋Ȃ��v�ƌ��������B �������|�[�����g���\���ɂȂ邱�Ƃ��l�������Ƃ͂Ȃ������B �@���ǁA�u�C�G�X�^�f�C�v�̓V���O���J�b�g����邱�Ƃ��Ȃ��i�A�����J�A���{�ł̓V���O���J�b�g���ꂽ���j�A�w�w���v�x�̂P�ȂƂ��Ăa�ʂɎ��߂��P�X�U�T�N�Ƀ����[�X���ꂽ�B �@�u�C�G�X�^�f�C�v�ł̌o�����u�G���i�[�E���O�r�[�v�ɂȂ��������Ƃ͂܂������Ȃ����낤�B �@�`�F���⃔�@�C�I�����A���B�I�����g�p���Ȃ�����A�ߏ�ȑ������{�����ƂȂ��A����I�ł͂����Ă������ăZ���`�����^���Y���Ɋׂ邱�Ƃ��Ȃ����Â���͋ɂ߂ă��b�N�I�ł���A���ꂱ�����܂��Ƀr�[�g���Y�I�ł���B �@�c�M�^�[��h�����Ȃ��ł����b�N�͂ł���Ƃ������Ƃ��ؖ����Ă��邵�A�����ɃX�g�����O�X���g���Ă����[�h���y�ɑ��邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��ؖ����Ă���悤�ɂ��v����B �@�r�[�g���Y�͂��ł��V���A�X�ɂȂ肷���邱�Ƃ��������B �w�T�[�W�F���g�E�y�p�[�`�x���u�A�E�f�C�E�C���E�U�E���C�t�v�Ńh���}�e�B�b�N�ȑ�c�~���}������ɕ������Ă���̂͋t��]�ɂ�郁���o�[�̊�Ȃ����肾�������A�w�A�r�C���[�h�x�������I�ȁu�W�E�G���h�v�Ŗ�����邩�Ǝv���A�u�n�[�E�}�W�F�X�e�B�v�ɂ������茨��������H�킳���B �@�u�t���[�E�A�Y�E�A�E�o�[�h�v�̃A�E�g���ɑ~���炳���E�N�����́u���̂܂܂ŏI���Ǝv���Ȃ�B�v�Ƃł������Ă��邩�̂悤���B �u�V���A�X�ɂȂ肷���Ȃ��v���Ƃ́u�炢���Ƃ�������v���o�v�[���l���L�̒m�b�Ȃ̂����m��Ȃ��B �@�w���҂̑咬�z��Y�����A���鎞�A�����J�[���E�x�[���Ɂu���[�c�@���g���āA�ǂ����t���ׂ��ł��傤���H�v�Ɛq�˂��B���̂Ƃ��x�[���́u���[�c�@���g�̓��}���e�B�b�N�ł����Ă��A�����ăZ���`�����^���ł����Ă͂����Ȃ��v�Ɠ������Ƃ����B �@�u�y�������݁A�d���������ԁv�ƕ\������郂�[�c�@���g�̉��y �@�����݂�\������̂ɂ���ɗD������Y��Ȃ��������A�V�^ࣖ��ȋȒ��̒��ɂ������݂��Ƃ邱�Ƃ��ł���B �@�x�[�g�[�x���̂悤�ɋ��̓������ׂĂ��炯�o���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B �@���ʂɂ�����̂����̂܂ܕ\�ɏo���̂ł͂Ȃ��A�}�����\���ɂƂǂ߂邱�Ƃ��������Ē������̂̐S�ɐ��ݓ�����̂��Ƃ������Ƃ��A���[�c�@���g�͕\���҂Ƃ��ĉ����Ă����B �@�r�[�g���Y�͂����Q�O���I�̃��[�c�@���g�ƌ�����B�ł́A�r�[�g���Y�ƃ��[�c�@���g�A���҂ɋ��ʂ�����̂Ƃ͉����B �@�V���̍�Ȃ̍˔\�͂����܂ł��Ȃ����Ƃ����A���҂̍���ɋ��ʂ��Ă�����̂Ƃ́A���������Ń��[���A��Y��Ȃ��X�s���b�g�i���_�j�Ƃ�肷���Ȃ��o�����X���o�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B �@���ꂱ�������S�ȉ��y���`�����Ă��鍪��ɂ�����̂��ƍl����B
|
||||
| �r�[�g���Y�̗����� | ||||
�@�X�e�[�W�������ĉE���ɃW���������Ɍ҂ŗ����ă��[�h���Ƃ�A�����Ƀ|�[���ƃW���[�W����{�̃}�C�N���͂���Ō��������悤�ɗ����A�R�[���X�Œǂ�������B �@�W�����ƃW���[�W�̊ԁA����ł̓����S���h������@���Ă���B�r�[�g���Y���v�������ׂ�Ƃ��A�����̐l�������C���[�W���낤�B�@�����̃X�[�c�𒅂āA�T�C�h�S�A�̃u�[�c�𗚂��A���b�P���o�b�J�[�A�փt�i�[�A�O���b�`�̃M�^�[������A���̑��`�ŗ��ĂΒN�����^���Ȃ��r�[�g���Y�̃g���r���[�g�o���h���Ǝv���ɈႢ�Ȃ��B �@�V���G�b�g�����������Ńr�[�g���Y�Ƃ킩�邱�̃t�H�[���[�V�����̓}�b�V�����[���J�b�g��݂Ȃ��X�[�c�ƂƂ��ɏ����r�[�g���Y���ے�������̂ł���B �@�������A����ŁA�S�����{�[�J�����Ƃ�̂Ƀt�����g�̂R�l�Ƀ}�C�N���Q�{�Ƃ������̃t�H�[���[�V�����͉̂��̂ɓs���̂悢�X�^�C���Ƃ͌�������̂��B �@�o���h����������Ƃ�����l�͂킩��Ǝv�����A�Q�l�łP�{�̃}�C�N���g���ꍇ�A�ǂ�ȂɊ���������ĉ̂��Ă��P�l�ʼn̂����ɔ�ׂ�Ɛ��͏E���ɂ����A���R�o�����X�͈����Ȃ�B �@�ł́A���̃t�H�[���[�V�����͂��A�ǂ̂悤�ɂ��ďo���オ�������̂��낤���B �@�r�[�g���Y�Ɋւ��邠���鎖�͌�����������Ă���ɂ�������炸�A�M�҂��m����肱�̂��Ƃɂ��ď����ꂽ���̂͂���܂łȂ������悤�Ɏv���B �@����͂��̂��Ƃɂ��čl���Ă݂����B �@�܂��A���̃t�H�[���[�V���������m�����ꂽ�����c���ꂽ�ʐ^�Ɖf������T���Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B �@�P�X�U�P�N�Ƀ����Q���E�t�H���}�[*���n���u���O�̃g�b�v�E�e���E�N���u�ŎB�e�������C�u�ʐ^�ɂ̓W�����A�|�[���A�W���[�W�����ꂼ��̃}�C�N�ʼn̂��p�����߂��Ă���B �@�g�b�v�E�e���E�N���u�ɏo�������̂͂S���P������V���P���܂łł������̂ŁA�ʐ^�͂��̎����ɎB��ꂽ���̂��B �@�X�e�[�W��̕��т́i�������āj�E����W���[�W�A�|�[���A�W�����̏��ł���B�܂��ʂ̎ʐ^�ł͉E����W�����A�|�[���A�W���[�W�̏��ƂȂ��Ă���A���̍��͓��ɕ��я������܂��Ă����킯�ł͂Ȃ��A���̎��X�ŕς���Ă����悤���B �@�r�[�g���Y�����t���Ă���f���ōł��Â����̂́A�P�X�U�Q�N�W���Q�Q���ɃO���i�_�E�e���r�����^�����L���o�[���E�N���u�ł̃X�e�[�W�ł���B �@���̎����^���ꂽ�̂́A�hSome Other Guy�h�ƁhKansas City/Hey-Hey-Hey�h�̂Q�Ȃ����A��������̂́hSome Other Guy�h�݂̂ł���B �@�}�C�N�͂Q�{�ŃW�����ƃ|�[�����{�[�J�����Ƃ��Ă���B���т͉E���W�����A�����|�[���ł���B �������ɎB��ꂽ�Ǝv����f���ł́A�|�[���ƃW���[�W�������}�C�N�ʼn̂��p�����邱�Ƃ��ł��邪�A���т̓W���[�W�����Ń|�[�����E�ƂȂ��Ă���B �@���Ȃ݂ɁA���̂R���O�̂W���P�W���A�h���}�[���s�[�g���烊���S�Ɍ�サ�ď��߂ẴX�e�[�W���s���Ă���B �@���P�X�U�R�N�A�S���Q�P���̃G���p�C�A�E�v�[���ŎB��ꂽ�ʐ^�͋����[���B �@���т͉E����W�����A�|�[���A�W���[�W�̏������A�|�[���ƃW���[�W�̑O�ɂ͂Q�{�̃}�C�N������ɂ�������炸�A��l�̓����}�C�N�ʼn̂��Ă���̂��B �@�����N�̂W���Q�Q���ɂ̓T�U���v�g���Œn�������ǂ̃j���[�X�ԑg�̎��^�̂��߂ɁhShe Loves You�h���^�����t���Ă���B���̎��B��ꂽ�ʐ^�ł́A�E����W�����A�W���[�W�A�|�[���̏��ŗ����A�|�[���ƃW���[�W�̓����}�C�N�ʼn̂��Ƃ����`�����邱�Ƃ��ł���B �@�P�P���S���A�W�����́u��W�����W�����v�����ŗL���ȃ��C�����E�o���G�e�B�E�p�t�H�[�}���X���s��ꂽ�B ���̂Ƃ��̖͗l�́A�U�E�r�[�g���Y�E�A���\���W�[�Ŋς邱�Ƃ��ł��邪�A���̃t�H�[���[�V���������S�ɏo���オ���Ă���̂��m�F�ł���B �@�ȏ�̂��Ƃ���A�P�X�U�R�N�̂S���ȍ~�A�Ă܂łɂ̓t�H�[���[�V�������o���オ�����ƍl���邱�Ƃ��ł���Ǝv���B �@���ɁA���ꂪ�N�̃A�C�f�A�������̂����l���Ă݂����B �@�P�X�U�Q�N�̂P���Q�S���A�����Ƀr�[�g���Y�̃}�l�[�W���[�ɂȂ����u���C�A���E�G�v�X�^�C������n�߂ɍs�����̂́A�r�[�g���Y���u������Ƃ�����v���Ƃ������B �@�C���[�W��������ꂽ���̂ɂ��邽�߁A�v�W�����̑���ɃX�[�c�𒅂��A�X�e�[�W�ł̈��ݐH���∫�ӂ������~�߂����A���Ԃ��I�Ȃ��s������������肾�����X�e�[�W�\������������l�������̂ɕς����B���t�I����̂����V���G�v�X�^�C���̎w���ɂ����̂��B �@���̂Ƃ��G�v�X�^�C���̓r�[�g���Y�̃C���[�W�����}�邤���ŁA�X�e�[�W��̕��т����܂������̂ɂ����ق����悢�ƍl�����̂ł͂Ȃ����낤���B �@����𗠕t����悤�ɁA�G�v�X�^�C�����}�l�[�W���[�ɏA�C�����U�Q�N�ȍ~�A�W�������E�A�|�[�������Ƃ�����{�I�Ȍ`�͌Œ肵�Ă���B �@�ł́A���̂��̃|�W�V���j���O�Ȃ̂��B �@���̓_�Ɋւ��ẮA��͂�|�[�����������ł��������Ƃ��v�����낤�B �@�M�^�[�̃w�b�h���X�e�[�W�̗��T�C�h�ɗ����J���悤�Ɍ������̌`����Ԍ��f�����ǂ��̂��B �@���ɁA�}�C�N���R�{�ł͂Ȃ��Q�{�ł��闝�R���l���Ă������B �@�P�X�U�Q�N�U���U���A�A�r�C�E���[�h�̂d�l�h�X�^�W�I�ŏ��߂Ẵ��R�[�f�B���O�E�Z�b�V�������s��ꂽ�Ƃ��A�v���f���[�T�[�̃W���[�W�E�}�[�e�B���́A�g���[�_�[�h���N�������ɂ߂邽�߁A�e�����o�[�̃V���K�[�Ƃ��Ẳ��l�������������ƃG�v�X�^�C���ɓ`���Ă����B �@�����̓N���t�E���`���[�h���V���h�E�Y�̂悤�ɃV���K�[�ƃo�b�N�o���h�Ƃ����`�Ԃ��嗬�ł���A�r�[�g���Y�̂悤�ɂR�l�̃{�[�J���X�g��������A�n�[���j�[�ʼn̂����肷��O���[�v�͂���߂ċH�������̂��B �@�W���[�W�E�}�[�e�B���������͂��������������̕Ґ��ɂ�������Ă����̂��낤�B �@���̋����W�����ɂ��ׂ����A���b�N�X�̂����|�[���ɂ��ׂ����A�i�W���[�W�͑��̓�l�ɔ�ׂĐ��͗ǂ��Ȃ������j���낢����������A�u�\���͕K�v�Ȃ��B���̂܂܂݂�Ȃɉ̂킹�悤�B�v�Ǝv�����Ƃ����B �@���̎��_�ŃW�����ƃ|�[���i�{�W���[�W�j�Ƃ����{�[�J���̌`�Ԃ����肵���̂ł͂Ȃ����B �@�܂�A�W�����Ƀ}�C�N�P�{�A�|�[���ƃW���[�W�Ƀ}�C�N�P�{�Ƃ����`�ł���B �@�܂��A����̓o���h���̃q�G�����L�[��\���̂ɍł��킩��₷���`�Ԃ��Ƃ������邾�낤�B �@�X�e�[�W���ςĂ���҂ɂƂ��ẮA���������N�����[�_�[�ŁA�o���h���d���Ă���̂��Ƃ������Ƃ͎�̊O�d�v�Ȃ��ƂȂ̂��B �@���Ȃ݂ɁA�U�Q�N�̎��_�ł́A���C�u�ł̃��[�h�E�{�[�J���Ȑ��̓W�������ł������i�S�P�ȁj�A���Ƀ|�[���i�R�U�ȁj�A�W���[�W�i�P�X�ȁj�������B �@���̂��ƂɊւ��ẮA�u�j���[�E�~���[�W�J���E�G�N�X�v���X�v���̌��A�V�X�^���g�E�G�f�B�^�[�@�C�A���E�}�N�h�i���h�����̂悤�ɏ����Ă���B �@�u������x�͂����肵�Ă���̂́A�ނ炪��O�̑O�ɏ��߂Č��ꂽ�Ƃ��A�r�[�g���Y�́A�̂��������X�Ƃ��Ă���A�O���[�v�̂Ȃ��Ŗڗ����݂ł���W�����Ɂu�������āv����悤�Ɍ��������Ƃł���B�ނ͂������A�슴�I�ȈӖ��Ńr�[�g���Y�������̂��̂ƌ��Ȃ��Ă����B�܂��G���Ԃ̃O���[�v���`���A���ꂩ�玩���̑傫�ȖړI�̂��߂Ƀ|�[���𒇊ԂɈ������ꂽ�̂�����B �@���ꂪ�X�e�[�W�ł̃r�[�g���Y�̃|�W�V�����ɏے��I�ɕ\��Ă���B�W�����͂ЂƂ�Ő�p�}�C�N��O�ɉE�ɗ����A�|�[���̓X�e�[�W���ɂ��āA�W���[�W�Ƃӂ���łP�{�̃}�C�N���g���Ă���B�������A�����̃X�e�[�W�Ŋϋq��グ��G���f�B���O�ȂƂ��ĉ��t���ꂽ�Q�ȁhTwist And Shout�h �gMoney�h�́A��������W�����̋Ȃ��B�v �@�|�[���ƃW���[�W�̈ʒu�W�ɂ��ẮA�X�e�[�W���d�˂�ɂ�Ď��R�ɕς���Ă��������̂ł��낤�B �@�|�[�����E�ɗ������ꍇ�A�x�[�X�ƃM�^�[�̃l�b�N���d�Ȃ�A��l�Ŋ���������ĉ̂��̂ɂ͋ɂ߂ĕs�s���Ȍ`�ƂȂ�B �@�|�[�������A�W���[�W���E�ɗ��ĂA���݂�������܂��邱�ƂȂ��R�[���X�����邱�Ƃ��ł��邵�A��l�̎p�͂܂�ŋ��ɉf�����悤�Ō��f�����ǂ��B �@����ɁA�������邱�Ƃɂ��|�[�����\�����Ƃ�A�W�����ƃW���[�W���R�[���X������ꍇ�̃W���[�W�̃|�W�V�����ړ����X���[�Y�ƂȂ�B �@�W�����ƃ|�[�����n����A�W���[�W������ɉ����Ƃ��̃|�[���̑f�����X�}�[�g�Ȑg�̂��Ȃ��A�gShe Loves You���̂��r�[�g���Y���ς�ƁA���̃t�H�[���[�V�����͎��ɗǂ��l����ꂽ�ɂ߂č����I�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��ł��邾�낤�B �@�܂��A�M�^�[���E�A�x�[�X�����Ƃ����|�W�V���j���O�̓r�[�g���Y�ȍ~�A���[�����O�E�X�g�[���Y�A���[�h�o�[�Y�A�U�E�t�[�A�N���[���A���b�h�E�c�F�b�y�����A�f�B�[�v�E�p�[�v���Ȃǐ������̃o���h�ɂ���Čp������Ă������̂��B �@�\���O���C�e�B���O�A�{�[�J���X�^�C���A�R�[���X�n�[���j�[�A���t�e�N�j�b�N�A�g�p�y��A�A�����W�A���R�[�f�B���O�Z�p�ƃr�[�g���Y�������炵�����̂͌v��m��Ȃ����A����ɂƂǂ܂炸�X�e�[�W���O�ɂ��Ă����̉e���͂̂��������������ɂ͂����Ȃ��B �@����̍l�@�́A�M�҂̌���ꂽ�����ƒm���ɂ����̂ł��邽�߁A����Ȃ�l�@���K�v�Ǝv����B���炽�Ȏ����⎖�����������̕��͘A��������������K���ł���B *�P�X�U�O�N�Ƀn���u���O�Ńr�[�g���Y�ƒm�荇���A�A�X�g���b�h�E�L���q�w�A��N���E�X�E�t�H�A�}���ƂƂ��Ƀt�@�b�V������X�^�C���ɉe����^�����B �@�n���u���O����̃r�[�g���Y�̋M�d�Ȏʐ^���B�e���A���̂����̂P���̓W�����̃A���o���u���b�N���E���[���v�̃W���P�b�g�Ɏg�p���ꂽ�B ���P �@�U�O�N��̃}�C�N�͌��݂̂悤�ȁu�P��w�����v�ł͂Ȃ��������߁A������̉����O������̉��Ɠ������炢�E���Ă����̂ŁA�����}�C�N�̃R�[���X���\�������Ƃ̘b������B ���Q �@�u�U�E�r�[�g���Y�E�A���\���W�[�v�������ɂȂ�ꂽ���̒��ɂ́A�P�X�U�R�N�P���ɂ̓t�H�[���[�V�������������Ă����Ǝv������������邩���m��Ȃ��B �@Episode2�Ɏ��^�̃}���`�F�X�^�[�����ł́gShe Loves You�h�@�i�J���[�f���j���t���̓��{�����ɂ͂P�X�U�R�N�P���Q�O���ƃN���W�b�g����Ă��邩��ł���B �@�����A����ɂ��ẮA�ȉ��̂Q�̗��R����P�X�U�R�N�P�P���Q�O���̌��ł��邱�Ƃ��킩�����B �@ �r�[�g���Y�����̑��l�҃}�[�N�E���C�\���́u�U�E�r�[�g���Y�^�S�L�^�@vol.1 1957-1964�v�ɂ��A�P�X�U�R�N�P���Q�O���̓L���o�[���E�N���u�ɏo�����Ă���B�P���P�U���Ƀ}���`�F�X�^�[�łs�u�o�����Ă��邪�@�gShe �@Loves You�h�@�͉��t����Ă��Ȃ��B �A �������u�U�E�r�[�g���Y�^�S�L�^�@vol.1 1957-1964�v�̂P�X�U�R�N�P�P���Q�O���̍��ɂ́A���̓��̌����̂P��@�ڂ̃X�e�[�W�ŁgShe Loves You�h�ƁhTwist And Shout�h�@���B�e����A�y�����i�A�q�X�e���[��Ԃ̃t�@���A�@�@�W���[�N�������������o�[�̃R�����g�Ȃǂ��܂����ĕҏW���ꂽ�J���[�E�j���[�X�f��hThe Beatles Come To �@Town�h�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��A�P�Q���Q�Q������P�T�ԃC�M���X�̓���̉f��قŏ�f���ꂽ�@�Ƃ̋L�^������B ��v�Q�l���� �@�u�U�E�r�[�g���Y�^�S�L�^�@Vol.1 1957-1964�v�i�v���f���[�X�E�Z���^�[�o�ŋǁj �@�u�m�[�E�G�A Vol.21�@�r�[�g���}�j�A�ȂP�O�O�O���ԁv�i�v���f���[�X�E�Z���^�[�o�ŋǁj �@�u�U�E�r�[�g���Y�E�T�E���h�u�b�N�@Vol.2���C�u�сv�i�v���f���[�X�E�Z���^�[�o�ŋǁj
|
||||
| �r�[�g���Y�͉������痈���̂� | ||||
| �@�r�[�g���Y�̌̋����o�v�[���̓�ɂ̓E�F�[���Y�n�����L����A���ɂ͊C���u�ĂăA�C�������h������B �@���o�v�[���ɂ́A�E�F�[���Y�l��A�C�������h�l���吨�Z��ł���A�E�F�[���Y�l�͉̂���肭�A�A�C�������h�l�͋@�m(�E�B�b�g)�ɕx��ł���ƌ����Ă���B  �@�u�̂���肭�@�m(�E�B�b�g)�ɕx��ł���v�A����́A���Ƀr�[�g���Y�ɂ҂����蓖�Ă͂܂�����ł���A�ނ炪�����܂Ő��E���̐l�X�Ɉ����ꑱ���Ă������Ȃł���B �@�ł́A�����̓����͔ނ�̏o���ɗR��������̂ł��낤���A�ނ�ɂ̓P���g�i�A�C�������h/�E�F�[���Y/�X�R�b�g�����h�j�̌�������Ă���̂��낤���B�r�[�g���Y�͉������痈���̂��B �@����͔ނ�̃��[�c�ɔ����Ă݂����B �@���̃n���^�[�E�f�C���B�X�̂U�O�N��̖����u�r�[�g���Y�v�i���v�Ёj�ɂ��A �@�W�����̑c���W���b�N�E���m���̓A�C�������h�̃_�u�������܂�A�l���̑唼���A�����J�ŐE�Ɖ̎�Ƃ��đ���A�i�����̃P���^�b�L�[�E�~���X�g�����Y�̃����o�[�������Ƃ����B�j�̎�����߂Ă��烊�o�v�[���ɖ߂�A�����Ńt���b�h�i�W�����̕��e�j�����܂ꂽ�B �@�|�[���̗��e�̓A�C�������h�o�g�A�W���[�W�͕���̑c�����A�C�������h�o�g�B �@�����S�̃X�^�[�L�[�Ƃ������́A���Ƃ��ƃX�R�b�g�����h�̖k���A�m���E�F�[�ɂ��߂��V�F�g�����h��������o�����̂ƌ����Ă��邪�A�����S�̑c���̐��̓p�[�L���ŁA��e���č��������߁A�X�^�[�L�[�ɂȂ����̂��Ƃ����B �@��Ƀ����S�̓r�[�g���Y�E�A���\���W�[�̒��Łu�U�O�N��Ɏ����̉ƌn�}������Ă��炨���Ƃ������ǁA�Q���サ���k��Ȃ������v�ƌ���Ă���B �@�ȏ�̂��Ƃ���l����A�g�W�����E�|�[���E�W���[�W�̓A�C�������h�̌��������P���g�n�A�����S�ɂ��Ă͕s���h�Ƃ������ƂɂȂ�B �@���A����ŁA�u�u�����h�E�w�A�̂��Ȃ��e�`�a�S�͑S���P���g�n�v�Ƃ������͂U�O�N�ォ����m�̎����̂悤�ŁA�r�[�g���Y�Ƃ��e�����C���h�ł��ґz���s�ւ����s���W�����ɃX���[�t�B���K�[�s�b�L���O���������X�R�b�g�����h�l�V���K�[�\���O���C�^�[�@�h�m���@���A�����ăA�C�������h�̍����I�̎胁�A���[�E�u���b�N���F�߂Ă���B �@�|�[���ɂ��Ă͖��O������P���g�n�ł��邱�Ƃ�����������B �@�|�[���̐�McCartney�́gMc�h�́A�Q�[����Łu�c�̑��q�v�i���p��́hson�h�j�̈Ӗ��ŃA�C�������h�E�X�R�b�g�����h�n�̐��ɂ݂���B�G���i�[�E���O�r�[�ɏo�Ă���Father McKenzie�����l�ł���B �@�܂��gMc�h�Ɠ��l�̈Ӗ��ŁgO'�h��gFitz-�h������B �u���Ƌ��ɋ���ʁv�̃X�J�[���b�g�E�I�n��Scarlett O�fhara ���A�C�������h�n�ł���B �@���Ȃ݂ɃW���[�W�͏��\���E�A���o���gAll Things Must Pass�h�ł̎���̑��d�^���ɂ��R�[���X���ɁgGeorge O�fhara- Smith Singers�h�Ɩ��t���Ă���B�i�gMy Sweet Lord�h�ŌJ��Ԃ����}���g���gHalleluiah�h�gHare Krisha�h�Œ������̂�����j �@�ȉ��Ƀr�[�g���Y�i�W�����ƃ|�[���j�ƃA�C�������h�Ɋւ���G�s�\�[�h���Љ�Ă������B �@�V�Q�N�P���k�A�C�������h�Łu���̓��j�������v���N�������A�|�[���� �gGive Ireland Back To The Irish�h�i�A�C�������h�ɕ��a���j�\�B�i�a�a�b�ŕ����֎~�j �@�W�����́gSunday Bloody Sunday�h�gThe Luck Of The Irish�h�i��������gSometime In NewYork�@City�h���^�j�����̎������̂������̂ł���B �@�V�T�N�P�O���X���A�W�����̂R�T�̒a�����ɃV���[���E�^���E�E�I�m�E���m���a���B �@�t�@�[�X�g�l�[���gSean�h�́gJohn�h�̃A�C���b�V���l�[���ł���B�i���t���e�̓G���g���E�W�����j �@�O�Q�N�U���P�P���A�|�[���͖k�A�C�������h�A���i�n���B�O���X���[�ɂ��郌�Y���[��ŁA�w�U�[�E�~���Y�ƌ��������������B �@�|�[���͕ꃁ�A���[�����i�n���B�o�g�ł��邱�Ƃ���A���̏ꏊ�����Ɍ��߂��Ƃ����B
|
||||